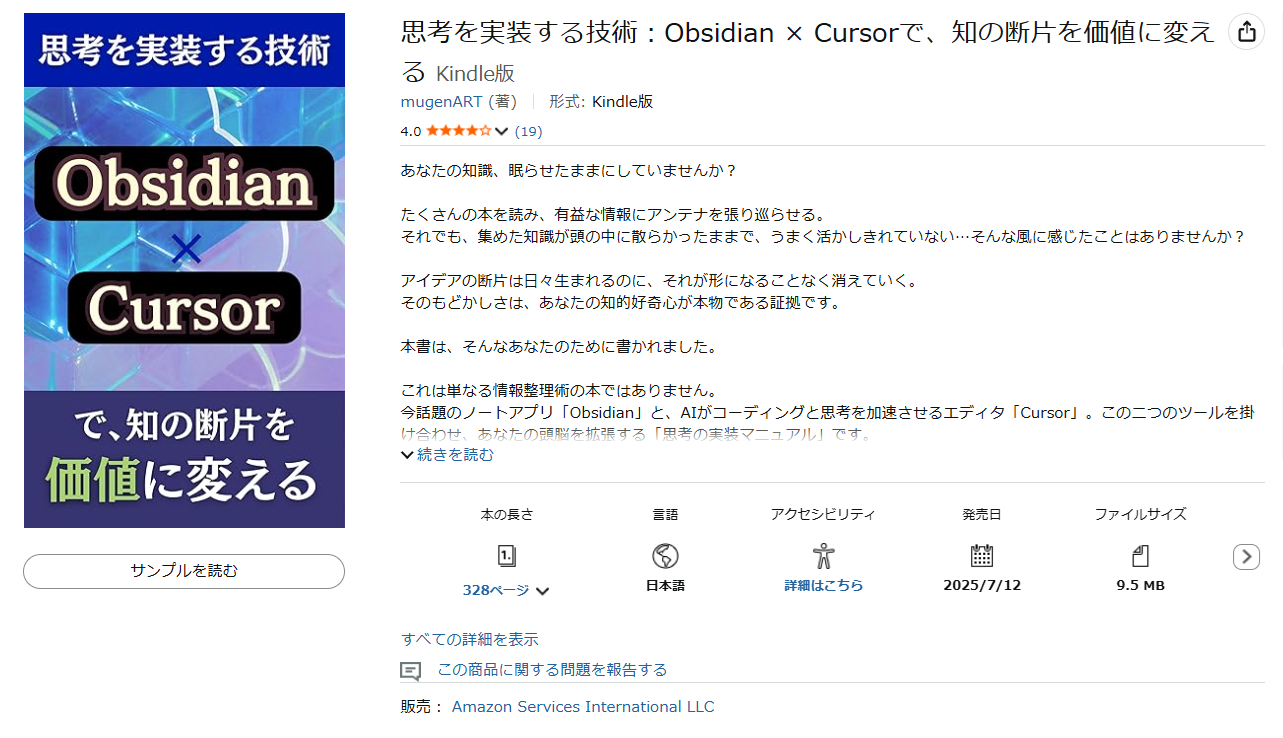文章を書こうとして、手が止まってしまうとき。
「何から書けばいいのか、わからない」
「うまくまとまらない」
「言いたいことが整理できていない」
そんなときにおすすめしたいのが、“問い”から始めるライティングです。
この記事では、Obsidianで「問い」を蓄積し、CursorでAIと対話しながら文章を育てていくという、まるで一人で編集会議をしているような思考の流れをご紹介します。
結論:良い問いを立てれば、自然と文章が生まれる
書けない原因の多くは、「結論が決まっていない」ことにあります。
でも、結論を決めなくても、“問い”を立てることは誰でもできます。
問いがあれば、考える方向が見えます。
問いがあれば、AIにも「考えるヒント」を渡せます。
Obsidianで問いをためて、Cursorで展開する。
これだけで「書けない」が「考えたい」に変わっていきます。
ステップ① Obsidianに“問いのメモ”をためる
まずはObsidianを開いて、思いついた「問い」だけを記録する専用ノートを1つ作ってみましょう。
ファイル名例:
- 1
2025-09-27_question-bank.md記録例:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
## 習慣化について考える問い
- なぜ「意志の力」では習慣が続かないのか?
- 「やめない仕組み」ってどう作る?
- 習慣化に失敗したとき、何を振り返ればいい?
- モチベーションと習慣、どちらを先に考えるべき?このように、考えたいテーマごとに問いをストックしておくと、
書けないときに「思考の入り口」を与えてくれます。
ステップ② 書きたくなった問いを1つ選んでメモに写す
次に、実際に文章にしてみたい問いを選びます。
選んだ問いを、下書き用ノート(たとえば drafts/ フォルダ)にコピーして、
その下に自分の答えや思考の断片を書き始めます。
例:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
## なぜ「意志の力」では習慣が続かないのか?
・疲れていると意志は働かない
・そもそも意思力には限界がある(筋肉のように)
・意思より環境やリズムのほうが続けやすい?この時点で文章になっていなくてもかまいません。
むしろ、「自分への問いかけ+メモの断片」という状態がベストです。
ステップ③ Cursorで開き、AIに“問いの編集会議”をしてもらう
Obsidianで書いた下書きファイルを、Cursorで開きます。
問いとメモを選択して、AIに「まとめ」「再構成」「展開」を依頼します。
プロンプト例①:構成の提案をしてもらう
- 1
- 2
この問いに答える文章を構成したいです。
どんな順番で話を展開すれば、読み手にわかりやすく伝わるか提案してください。AIの返答例:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
1. 問いの提示(なぜ意志の力では続かないのか)
2. 意志の限界についての背景説明(疲労・判断力の減退)
3. 習慣化のメカニズム(トリガー・環境設計)
4. 意志に頼らない方法の具体例
5. まとめ:仕組みづくりの視点の重要性この構成を見て、「あ、3→2→4の順の方が自然かも」と思えば、自分で順番を組み直してみましょう。
AIの構成提案は“問いに対する読者視点のヒント”として使えます。
ステップ④ 文章化したあとに、もう一度問いかける
AIと一緒に文章化できたら、もう一度Obsidianに戻って、「この問いはどう育ったか」を振り返ります。
- 1
- 2
- 3
- 4
## なぜ「意志の力」では習慣が続かないのか?
→ 文章にしてみて、「意志ではなくリズムと環境」という視点が自分の中にあることが分かった。
→ 次の問い:「どうすれば“無意識にできる環境”を作れるか?」こうすることで、「問い → 思考 → 文章 → 次の問い」という思考のサイクルが生まれます。
このループが、まさに一人編集会議のような働きをしてくれます。
補足:こんな問いは“育てやすい”
初心者のうちは、以下のような問いから始めると考えやすく、AIとも連携しやすくなります。
✔ WHY型(理由を深掘る)
- なぜ○○が大切なのか?
- なぜうまくいかないのか?
✔ HOW型(方法を考える)
- どうすれば○○できる?
- 何を変えれば続けられる?
✔ IF型(仮定で考える)
- もし○○だったらどうなる?
- ○○をやめたらどうなる?
こうした問いは、自分の考えとAIの視点が交差しやすく、文章としても自然に広がりが出てきます。
一人で悩まなくていい、“問い”があれば書き出せる
書こうと思っても書けないとき、
何を書けばいいか分からないとき、
自分を責めてしまう必要はありません。
問いを立てるだけでも、立派な思考です。
その問いに一言でもメモを書けば、もうそれは「書き始めている」状態です。
そしてCursorのAIは、その小さな問いを一緒に育ててくれる相棒です。
まとめてくれたり、例を挙げてくれたり、違う視点をくれたりする存在として、
ときに自分より冷静に、でも親しみをもって向き合ってくれます。
まずは今日、ひとつの問いを書いてみてください。
それだけで、次の思考が自然と始まります。
ObsidianとCursorの連携については、下記のページで実際に読んで良かった書籍を紹介しています。
気になる方はチェックしてみてね。Kindle Unlimitedに入っている人は無料で読めます。