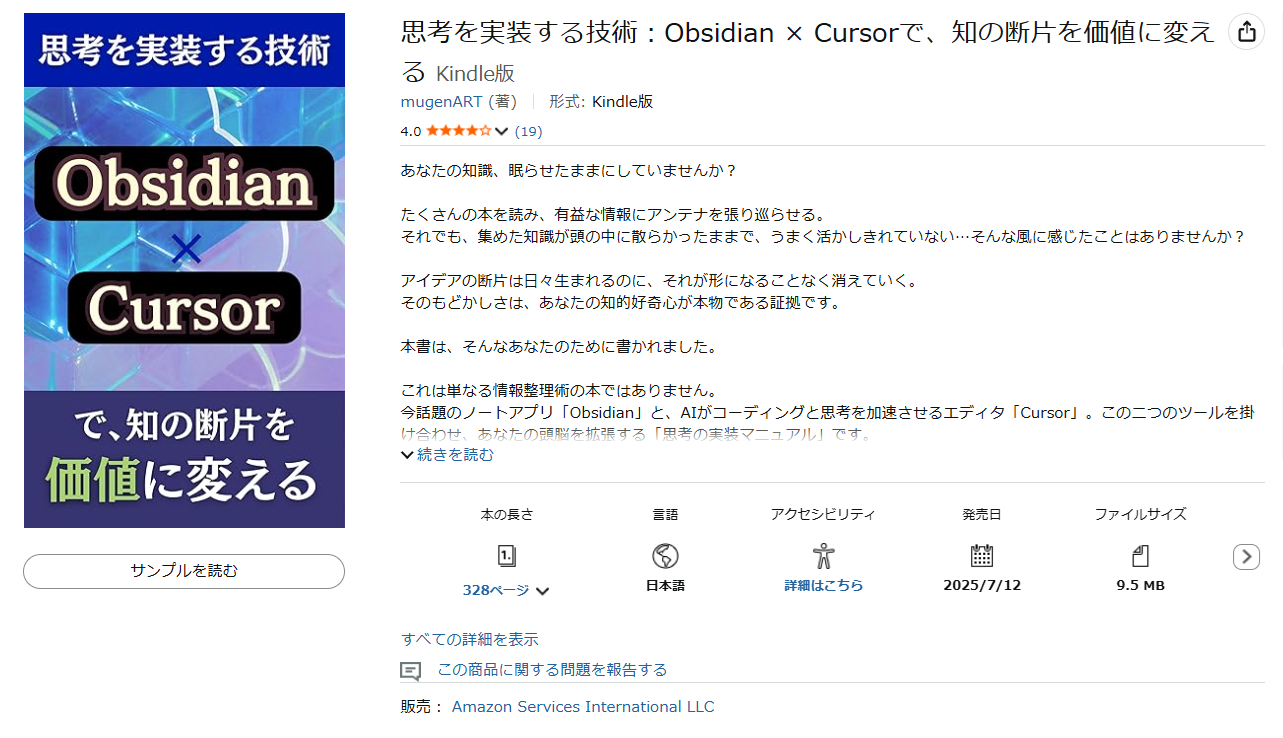本を読んで「これは大事だ」と思った言葉を、Obsidianにメモする習慣がある人は多いと思います。
でもその後、それらの引用をどう活かすかとなると、意外と悩むものです。
- 引用ばかりで、文章がバラバラになってしまう
- 自分の考えとどうつなげればいいかわからない
- 説得力のある文章にまとまらない
そこで今回は、Obsidianに集めた読書メモや引用を、CursorでAIと一緒に自然に文章へと育てていく方法を紹介します。
引用を“素材”として文章に“織り込む”という感覚を大切にした、初心者向けのやさしい執筆術です。
結論:引用は「核」ではなく「布に織り込む糸」だと考える
文章を書き始めたばかりのころは、
「いい引用があるから、それをもとに書こう」と思いがちです。
でも、引用そのものはあくまで補強材料や話題の“起点”であって、
あなた自身の視点や体験と結びついてこそ、生きた文章になります。
だからこそ、引用のあとに“自分の声”を加えるという意識が大切です。
そのために使えるのが、CursorのAIによる文章整形・補助機能です。
Obsidianで引用を集め、Cursorで文章化する。
この流れを丁寧に追っていきましょう。
ステップ① Obsidianで「引用+自分のひとこと」を蓄積する
まずはいつもどおり、読書中に気になった一節をObsidianにメモしていきましょう。
このとき、一緒に“自分の感想や考え”も1行だけでも書いておくと、あとがぐっと楽になります。
例:Obsidianの読書メモ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
## 『習慣の力』メモ(2025/09/27)
> 「習慣は、繰り返しによって脳に自動化される行動である。」
→ 無意識に行動が始まるようになるまでの“準備”が必要。意志だけでは難しい。
#読書メモ #習慣 #引用このように、「引用」→「自分のひとことコメント」という形で積み重ねていくと、
後からの再利用がとてもスムーズになります。
ステップ② 複数の引用を1つの下書きノートにまとめる
1つのテーマに沿った引用がたまってきたら、
それらを1つのMarkdownファイルにまとめましょう。
例:テーマ「習慣と意志力」
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
## 習慣と意志力に関する引用メモまとめ
> 「習慣は、繰り返しによって脳に自動化される行動である。」
→ 無意識に動けるようにするには、意志力だけでは足りない。
> 「人は環境によって動かされている。自分の意志ではない。」
→ 続けるには“仕組み”と“環境設計”が重要。意思に頼るのは消耗戦。
> 「やる気があるときに決めたことより、仕組みの方が確実に働く。」
→ モチベーション任せでは、継続性に欠ける。このように、テーマを軸に複数の引用と自分の考えを整理することで、
「AIに頼るための素材」がそろってきます。
ステップ③ Cursorで開いてAIに「文章化」してもらう
まとめたファイルを.md形式で保存し、Cursorで開きましょう。
そのまま全体を選択して、次のようにAIに指示します。
プロンプト例①:読み物として自然な文章に整えてもらう
- 1
- 2
この引用メモをもとに、読者にとって読みやすいコラム風の文章にしてください。
引用を自然に組み込みながら、自分の考えも展開する構成にしてください。AIの出力例:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
私たちは何かを習慣にしたいと考えたとき、つい「意志の力」で乗り切ろうとしてしまいます。
しかし『習慣の力』では「習慣は、繰り返しによって脳に自動化される行動である」と説明されています。
つまり、行動が自然に始まるような“仕組み”を作ることが重要なのです。
別の書籍では、「人は環境によって動かされている」とも語られています。
この言葉の通り、自分を責めるよりも、環境のほうを変えるほうが確実に効果が出ます。
やる気やモチベーションに頼るのではなく、
あらかじめ行動を起こしやすくする準備をしておく。
それが習慣づくりの本質だと、改めて気づかされました。このように、引用を「芯」にしつつ、自分の言葉が自然に乗ってくる構成が完成します。
ステップ④ 引用を「補足」や「締め」として活用する方法もある
引用は「冒頭」に置くばかりではなく、
「締め」や「補足」として登場させることで説得力が増すこともあります。
プロンプト例②:締めに引用を入れる構成
- 1
- 2
このメモをもとに、本文は自分の視点中心で書き、
最後に引用を入れて全体をまとめる構成にしてください。AI出力例(抜粋):
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
どうしても“やる気”に頼ってしまう習慣づくりですが、
実はそれこそが続かない原因でもあるのです。
準備や環境の工夫があってこそ、自然と続く行動になります。
「やる気があるときに決めたことより、仕組みの方が確実に働く。」
この言葉が、そのことを端的に表しています。このように、引用を“締めの一言”として効かせる構成もCursorではすぐ試せます。
補足:引用と著作権についての基本的な考え方
基本的に「短い引用であること」「出典が明記されていること」「主張の補強として使われていること」が守られていれば、
一般的な読書メモやブログでの引用は問題ないとされています。
とはいえ、出典をできるだけ記載する・自分の言葉を主にするという基本姿勢を持っておくと安心です。
引用は「集める」で終わりではなく、「語りたくなる文章」に育てる
Obsidianで集めた引用は、読書中のあなた自身の“心の動き”の記録でもあります。
それをそのまま眠らせておくのはもったいない。
Cursorという“編集パートナー”がいれば、
その引用が、文章の起点や締めくくり、問いかけの素材として新しく生まれ変わります。
- 書けないときは、引用を起点にする
- AIと一緒に文章に整える
- そこに自分の声を重ねていく
この流れを持っておけば、読書は“ただのインプット”で終わりません。
あなたの言葉で再構成された“新しい思考のかたち”としてアウトプットされていきます。
ObsidianとCursorの連携については、下記のページで実際に読んで良かった書籍を紹介しています。
気になる方はチェックしてみてね。Kindle Unlimitedに入っている人は無料で読めます。