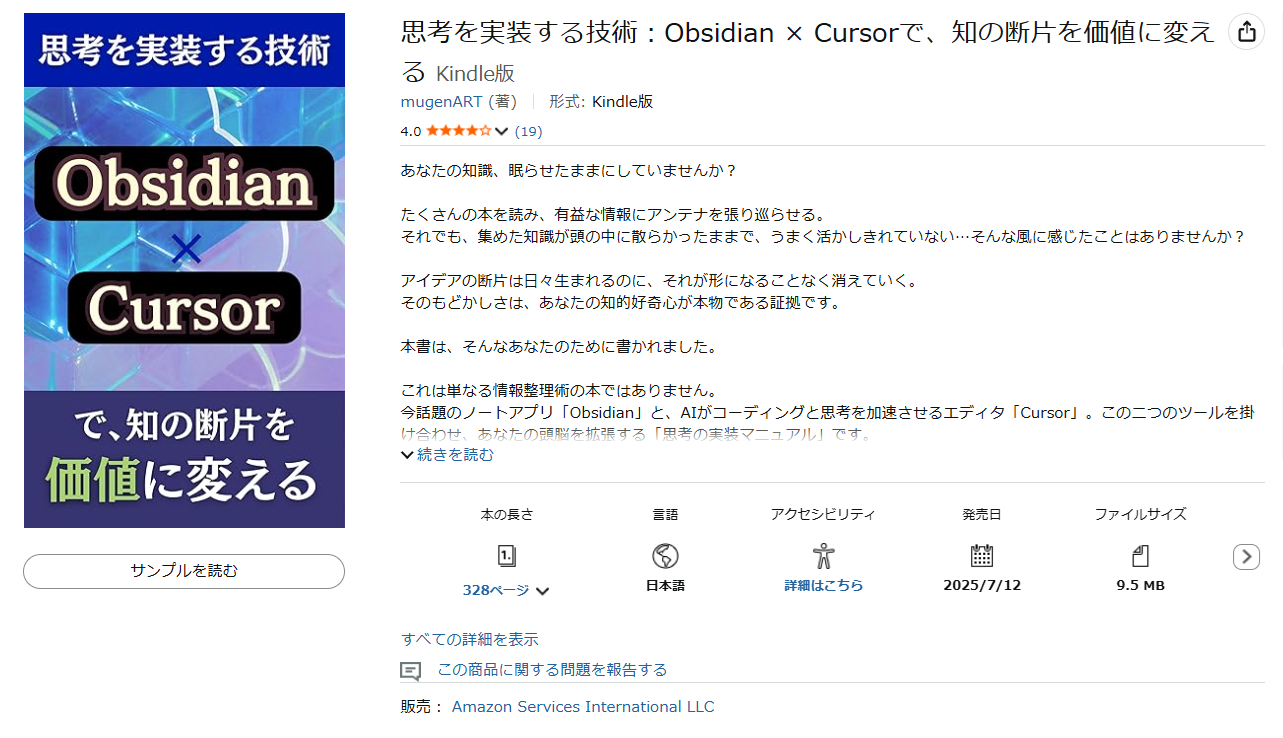よくある内容は「Obsidianでメモを書く → Cursorで整える」という流れですが、この記事では逆を考えてみます。
「CursorでAIに下書きを任せ、Obsidianでじっくり育てていく」という方法も、とても有効です。
今回はこの“逆流型ワークフロー”について、背景と理由、やり方を具体的に解説します。
結論:AIに“書き出し”を任せると、思考のきっかけが生まれる
人間にとって一番エネルギーを使うのは、「最初の1行を書くこと」です。
言い換えれば、「書き出しのハードル」を下げるだけで、書くことそのものが楽になります。
CursorのようなAIエディタを使えば、
自分の代わりに“たたき台となる文章”をさっと書いてくれるので、最初の壁を簡単に超えることができます。
そして、そのたたき台を Obsidianで読み直しながら、自分の言葉に置き換えて育てていく。
これが“逆流型”の基本の流れです。
なぜ逆流型が効くのか?背景を少しだけ
AIを使うと「考える力が落ちるのでは?」という不安の声もあります。
けれど実際は逆です。
- AIの書いた文章を読む
- 違和感に気づく
- 自分の中にある「伝えたいこと」に気づく
この流れを繰り返すことで、自分の思考が引き出されていくのです。
つまり、AIが“思考の素”を先に差し出してくれることで、内省が深まるという働き方になります。
ステップ① Cursorで「ざっくり書いてもらう」
まずはCursorで、書きたいテーマをざっくり指定してAIに下書きを作ってもらいます。
例:テーマ「習慣化のコツ」
Cursorの新規ファイルで、次のようなプロンプトを書きます:
- 1
- 2
「習慣化のコツ」というテーマで、初心者向けのブログ記事の下書きを800文字ほどで書いてください。
内容は、毎日やらなくても続く方法や、意志ではなく仕組みで続ける工夫に触れてください。するとAIが次のような下書きを出力します:
- 1
- 2
- 3
- 4
習慣化は「毎日続けること」と思われがちですが、実は「やめない仕組み」をつくることが鍵です。
毎日やろうとするより、「忘れたら明日やればいい」と考えることで、気持ちが楽になります。
続けるためには、意志よりも環境が大切です。
たとえば、目につく場所に道具を置くだけでも効果があります。この段階では「自分の言葉じゃないな」と感じても構いません。
むしろそこが出発点です。
ステップ② Markdownファイルとして保存してObsidianへ
AIの下書きができたら、そのまま.md(Markdown)ファイルとして保存します。
ファイル名の例:
- 1
2025-09-25_習慣化のコツ_AI下書き.mdこのファイルを、Obsidianで読み込めるVault内の任意の場所(例:03_draft/)に移動しておきましょう。
Obsidianはフォルダ内のMarkdownを自動で読み込むので、そのままエディタとして読み直し→修正ができます。
ステップ③ Obsidianで「自分の言葉に置き換えていく」
ここからがいちばん大事なフェーズです。
AIの下書きを、読みながら違和感のある部分を書き換えていきます。
修正ポイントの例:
- 「この言い方は少し固いかも」
- 「自分ならこういう例を使いたい」
- 「この順番、逆にした方が読みやすいかも」
たとえば、先ほどのAI文:
- 1
習慣化は「毎日続けること」と思われがちですが、実は「やめない仕組み」をつくることが鍵です。これをObsidianで読み直しながら、次のように書き換えることができます:
- 1
- 2
「習慣=毎日続けるもの」という思い込みがあるかもしれません。
でも実際は、「たまに抜けてもやめない仕組み」のほうが長続きします。このように、AIの下書きを素材として、自分の視点を重ねていく作業が、思考の整理と文章の深まりにつながっていきます。
補足:このワークフローの良さとは?
ここまでの流れで、次のようなメリットがあります。
- 書き出しに悩まなくて済む(AIが0→1を担う)
- 違和感から自分の視点を掘り起こせる
- 書き直しながら、内容が自然に自分のものになる
- Obsidianでタグ付けやリンクができるので知識が育っていく
特に初心者の方にとっては、「ゼロから考えて書くより、たたき台を育てる方が続けやすい」という実感が得られやすいと思います。
よくある不安とアドバイス
Q:AIの書いたものをそのまま使っていいの?
→ 必ず自分の目で読み直して、納得できる表現に直してください。
Obsidianで編集する過程が「自分の言葉に変える」大事な時間になります。
Q:下書きがイマイチなときはどうする?
→ そのまま捨てても大丈夫です。
むしろ「なんでイマイチに感じたのか?」を1行だけメモに残しておくと、思考が深まります。
まずは1つのファイルから試してみてください
この逆流型ワークフローのよいところは、1回5分でも試せるという点です。
- テーマを思いつく
- Cursorで下書きをもらう
- Obsidianで読み直して育てていく
この3ステップだけで、自分の文章ができあがっていきます。
続けるうちに、CursorとObsidianが「共著者」のような存在になってくるはずです。
ObsidianとCursorの連携については、下記のページで実際に読んで良かった書籍を紹介しています。
気になる方はチェックしてみてね。Kindle Unlimitedに入っている人は無料で読めます。